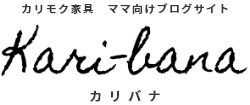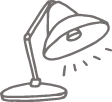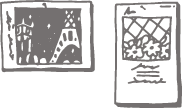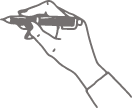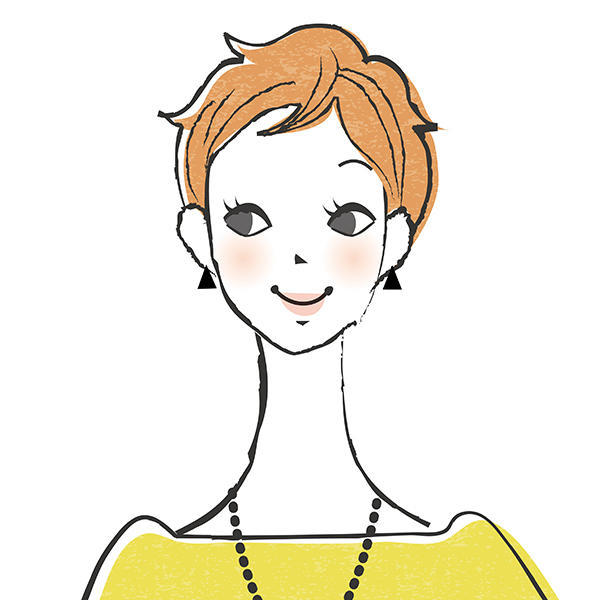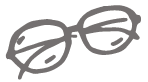小学生の片付け問題!収納の工夫とサポートで片付け習慣を育てよう

子どもがなかなか片付けをしてくれないと、悩んでいませんか?
できれば自分で片付けをする習慣を身につけて欲しいと思っていても、思い通りに動いてくれずイライラしてしまうこともありますよね。
忙しい毎日、急いでいるときには子どもを誘導する余裕がなく、代わりに片付けてしまうケースもあるでしょう。小学生になったら、おもちゃや遊び道具だけでなく学用品も増えて、子ども自身での管理が大変になってきます。
ますます、片付けができなくなるのではないかと心配しているママ・パパも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、小学生の子どもが自分で片付けができるような収納環境の作り方や、どんなサポートをしてあげるとよいのかを詳しくご紹介します。
小学生が片付け上手になる収納3つのポイント

小学生になると、これまでの生活にはなかった学校での時間が増え、毎日のルーティンが大きく変化します。学習に必要な教科書やノート・文房具など、身の回りのものも一気に増えるため、片付ける行為自体がストレスになってしまうかもしれません。
そこで、子どもにとって「わかりやすい」収納環境を作ってあげることが大切です。
ポイント1.収納場所を決めよう!
大人の収納計画でも重要なポイントの一つですが、まずは「ものの定位置」を作りましょう。この時、次の点に気をつけてみてください。
- 子どもにとって使いやすい高さ・場所を考える
- おもちゃなどの遊ぶものと学習に使うものは分ける
「手が届かない」「(高すぎて)見えない」など、小さなストレスが子どものやる気を損ねてしまいます。自分で片付けをするには、難しくない・大変ではないことが大切です。
小学校に入ると、これまでとは異なる生活習慣の「学習時間」が増えます。遊びの道具としっかり分けて収納することで、遊びと学習の時間の区切りもつけやすくなるでしょう。例えば、学習用の道具は机の近くに収納すると、自然に机に向かう習慣を促せます。
ポイント2.一目でわかるシンプルな収納スペース
何をどこに片付けるかを、できるだけわかりやすくしましょう。大人の感覚では、つい細かい分類で分けたくなるかもしれません。
しかし、子どもはルールが複雑になると面倒に感じてしまいます。
また、低学年くらいの子どもは一つひとつ片付ける場所を、なかなか覚えられないかもしれません。
一目でわかるようにラベリングをしたり、カラーボックスで色分けをしたり、子どもでも判別しやすいようにしましょう。
好きなキャラクターが付いている、おしゃれなアイコンやイラストで表示されているなど、子どもが喜ぶ工夫をしてみてくださいね。
ポイント3.ものを減らしてすっきりさせる
収納スペースにも限りがあります。ものを減らして、片付けやすく・探しやすい状態にするようにしましょう。
必要なものだけを子ども部屋に置くようにするため、使っていないおもちゃなどを整理します。いるもの・いらないものを選ぶプロセスは、子どもといっしょに行ってください。
ものを大切にする情緒を育むきっかけにもなりますよ。
そもそも、子どもが片付けられないのはどうして?
小学生になったからと言って、すぐに片付けができるわけではありません。
片付け習慣は小学校にあがる前から、親といっしょに少しずつ経験して身についていくものです。
また、生活習慣が変わることで、これまでできていたことも上手にできなくなってしまう可能性もあります。
年齢に関わらず、子どもが片付けをできない理由を考えて、親がしっかりサポートをしてあげることが大切です。
「片付ける」の意味をきちんと理解していない
大人が考える「片付ける」を、子どもは正しく理解できていないかもしれません。
例えば、「ものを移動させる=片付ける」と認識している場合があります。また、片付けをしなくても遊びや食事などは継続して行えるため、必要性がないと思っているケースも考えられます。
「気持ちよく過ごせる」「大切なものをなくしにくい」など、片付けをする必要性やメリットをポジティブに伝えてあげましょう。
収納スペースが十分に用意されていない
子ども自身も出しっぱなしにしたくないと思っていても、片付ける収納スペースが不足しているかもしれません。
小学生は、自分の好きなものもはっきりしてくるので、趣味のものなどが増えてしまいます。子どもの気持ちを尊重しながら、いらないものを処分するように促すなど、ものがあふれないようにしましょう。
このとき、あくまでも本人が決めるようにサポートしてあげてくださいね。
大人が片付けてくれると考えている
「言ってもやってくれない」「急いでいるから」と、大人が片付けてしまっていませんか?多くの場合、子どものとって片付けは楽しいことではありません。誰かがやってくれると思うと、つい人任せにしてしまいます。
きれいな部屋、整理整頓されている棚が、子どもにとっても快適であると感じさせることが大切です。
収納上手な小学生になるためにママ・パパができること
大切なのは、小学生の子どもが「自分から」片付けができるようにすることです。
「収納場所をつくる」「収納家具を用意する」など、親がサポートしながら、子どもが自主性をもって片付けができるように導いてあげてください。
また、片付けができないことを叱る・注意することも、ときには必要ですが、できたときにほめてあげてくださいね。
子どもが片付けを楽しい、心地よいと感じられる環境にしてあげましょう。
本人の大切にしたい「もの・こと」を尊重する
小学生になると、自分の好きなものやこだわりがはっきりしてきます。
やみくもに「片付けなさい」「捨てなさい」、あるいは「片付けないなら全部捨てるよ」と伝えるのは逆効果です。親から見ていらないものでも、本人が必要だと感じているものは、すぐに否定しないようにしましょう。
子どもの声にしっかり耳を傾けて、必要なものと不要なものをいっしょに選んであげてください。
子どもの描いた絵や工作で作ったものなどは一定期間飾る、期限を設けて一度保管する、写真に撮って実物は処分するなど代わりの提案をしてあげてもよいかもしれません。
親子でいっしょに収納場所や方法を見直す
一人ではどのようにすればよいかわからず、片付けができないケースもあります。
はじめは、親が先に「ランドセルを棚に置こう!」「プリントはファイルにとじよう!」などと具体的にするべきことを示しながら声をかけて、初動をうながしてあげてください。
しかし、大人が決めたルールを与えるだけでは自主性が芽生えません。片付けのルールを子どもに考えさせて、大人はアドバイスをするようにしましょう。
答えは子ども自身が出すようにするのが大切です。
小学生が自ら片付ける収納ルーティンを作る
収納場所を決めるだけでなく、子どもの一日の生活リズムのなかに片付けを取り入れてみてください。
学校から帰ったら、ランドセルを片付ける。ごはんを食べる前に、おもちゃや学用品・教科書などを片付けるなど、生活のルーティンに合わせて流れをつくってあげると、自然に片付ける習慣が身につくでしょう。
また収納場所をルーティンにあわせた動線上の位置に設けると、よりスムーズな流れを作れます。
小学生の生活習慣に合わせた収納環境を整えよう

小学生の子どもが、率先して片付けを行うためには、子どもの生活に即した収納環境を作ってあげることが大切です。
また、本人が片付けられた空間が心地よいと感じられるように、精神面でもサポートをする必要があるでしょう。
子どもの成長にあわせて、フレキシブルに活用できる収納家具を用意して、子どもの片付ける力を育ててあげてくださいね。
次の記事では、カリモクの学習机の近くで活用できるオープン収納や、移動させられるキャスター付きの収納をご紹介します。