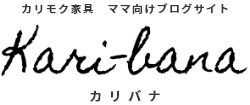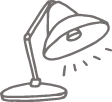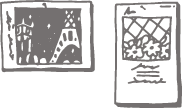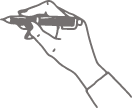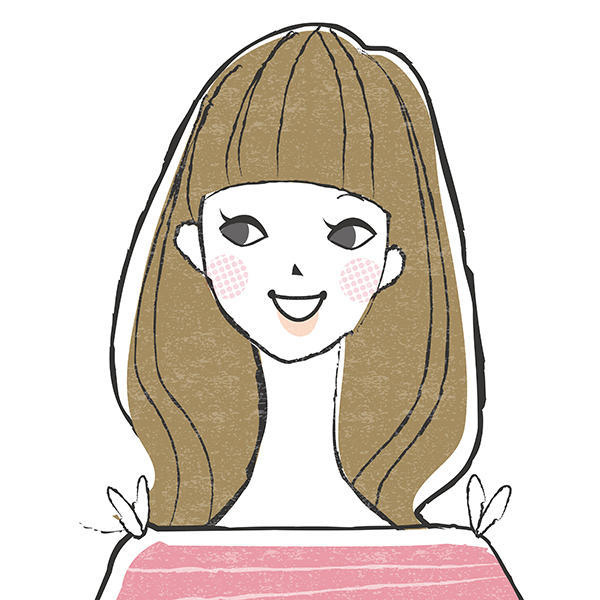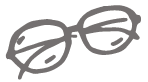自分で片付けられる子に!子どもに片付けの習慣がつく声掛けや収納方法

子どもに片付けの習慣をつけさせたいけれど、どうやったらいいのか悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか?おもちゃが散らかっていてもなかなか片付けてくれなくて、ついイライラしてしまうこともあると思います。
子どもが自ら片付ける習慣を身につけるには、ママパパの関わり方や片付けの仕組みづくりが大切です。そこで今回は、子どもに片付けの習慣をつけさせるためのテクニックを紹介します。
大きくなっても片付けがスムーズにできる子どもに育てたいという人はぜひ参考にしてくださいね。
片付けをするといいことがあると子どもが思えるように

子どもが進んで片付けられるようにするには、「片付けをするといいことがある」と子ども自身が思えるようにすることが大切です。片付いている状態を一緒に確認しながら「お片付けしてきれいになると使いやすくて気持ちいいいね」「広いスペースで遊べるね!」と具体例を上げ、子どもが片づけてくれたときは「お部屋がきれいになってうれしい!ありがとう」と感謝を伝えてみるのもいいでしょう。
片付けをはじめるのは2歳頃から。「お片付けを一緒にしよう!」と声をかけてやり方を見せながら、始めてみましょう。
3~4歳になって、ある程度習慣づいてきたら、子どもだけでさせることも大切です。しまう場所が間違っていたり、ぐちゃぐちゃに入っていたりしても、とりあえず1人で片付けることを経験させましょう。1人で片付けられると達成感が得られるので、次もまた自分で片付けようという気持ちにつながるのではないでしょうか?
どうしても1人で片付けるのが難しい場合はママパパが全部やってしまうのではなく、手伝いながら一緒に片付けるようにしましょう。
子どもに片付けを習慣化させるための上手な声掛け方法
子どもが片付けをする時には、親の声掛けが大切です。特に小さいうちは声掛けによって片付けのやる気が大きく変わってきます。そんな時に役立つ声掛けテクニックについて紹介します。
片付けを遊び感覚にして楽しめるようにする
子どもが進んで片付けるようにするには、片付けを嫌な作業ではなく楽しいものと感じさせるのがコツ。片付けも遊び感覚で楽しめるように声掛けしていきましょう。
例えば「ママが洗濯物をたたむのと、○○ちゃんがお片付けするのどっちが早いかな?」と競争にしてみたり、「何個のおもちゃを片付けられるかな?」とゲームのようにしてみたりするといいですね。
また、「このおもちゃはどこがお家だったかなぁ?」とクイズ風にするのもよさそうです。それでもなかなか片付けようとしない場合は「ママはこれを片付けるよ!○○ちゃんはどれにする?」と片付けるものを選ばせて、気分を乗せていくのもいいでしょう。
子どもが楽しく片付けられるようにいろいろと声掛けを工夫してみてくださいね。
上手な褒め方のテクニック
片付けができたらしっかり褒めてあげたいですよね。そんな褒め方にも、いくつかのテクニックがあるんです。まず、片付けがすべて終わってから褒めるのではなく、片付けている間から褒めの言葉を掛けてあげましょう。
「お!片付けやってるね~!えらい!」「○○のおもちゃをちゃんとしまえてすごい!」など、片付けている最中に声掛けしてやる気がアップするようにします。
この時、具体的に褒めるのも大切です。「本を上手に立てて並べられたね」「カバンと帽子をちゃんとかけられたね」など、1つ1つのことに注目して子どもにも伝わりやすいように言葉をチョイスしてあげましょう。
また、褒めの言葉だけではなく、感謝の気持ちを一緒に伝えるとより効果的に!
「お部屋をきれいにしてくれてありがとう」「自分で片付けてくれて助かるなぁ~」「上手に片付けてくれて嬉しいな」など、素直な気持ちを伝えましょう。ママパパが喜んでくれると子どもも嬉しくなるもの。ママパパの役に立てたという気持ちが、自己肯定感アップにもつながります。
「片付けなさい」のNGワードに注意!
子どもが片付けをなかなかしてくれなくて、イライラしてしまった経験のある人も多いのではないでしょうか?
最初はおだやかな気持ちで「片付けようね~」と声掛けしていても、子どもが一向に片付けようとしないと、つい「片付けなさい!」「早くしなさい!」という強い口調になってしまうかもしれません。
しかし、そこはグッと我慢することが大切です。ママが強い口調になってしまうと、子どもは叱られるから片付けるという考えになり、叱られなければ片付けなくていいやと思ってしまいます。そのため、片付けられない子になってしまう可能性が......。
また、定番文句の「捨てるよ!」というおどしもNG。反発心が生まれて余計に片付けなくなります。そんな時は「ママがもらっちゃうよ~」という声掛けにチェンジするのがおすすめ。子どもも「ダメー!」といって片付けるようになるかもしれませんよ。
子どもが自分で片付けられる収納の仕組みづくりも大切

子どもが進んで片付けられるようになるためには、収納の仕組みがしっかりできていないといけません。どこに何をしまうのかをはっきりさせ、子どもが片付けやすい環境を整えてあげましょう。
ものの定位置を決める
子どもが片付けやすくなるためには、おもちゃでも園や学校で使う道具でもそれぞれに定位置を決めることが大切です。ものの住所が決まっていないと、片付けのたびにどこにしまっていいのか悩んでしまい、スムーズにできません。
どこに何をしまうのかしっかりと決めれば、子どもも片付けやすくなります。定位置を決める時は、なるべく使う場所の近くにするのがおすすめ。片付けのたびに遠くまで持っていかなければならないと大人だって億劫になってしまいますよね。子どもの動線をチェックしながらどこにしまうか決めていきましょう。
ざっくりとしたグループ分けにする
おもちゃなどの収納は、ボックスやバスケットを使って仕分けすることで片付けやすくなります。この時、細かく分けすぎてしまうと、子どもにとって片付けが難しくなって長続きしません。
積み木・乗り物のおもちゃ・ままごと道具・ぬいぐるみなど、ざっくりとグループ分けするようにしましょう。1つの収納スペースに1つのグループのものを片付けるようにして、小さい子どもでも簡単に片付けられるような仕組みを作ることが大切です。
どこに何があるか一目でわかるようにする
子どもは目で見て覚えるため、どこに何をしまうのか見た目ですぐにわかる収納にすることが大切。半透明のケースや引き出しを使ったり、オープンラックに収納したりなど、一目見ただけでどこに片付けるといいのかわかるようにしてあげましょう。
中身の見えないバスケットに収納するなら、大きなイラストのラベルをつけてあげるといいですね。
子どもの成長にあわせて収納を変化させる
子どもは成長することでできることも増え、持ち物も変化します。そのため、成長にあわせて収納を変えていくことも大切です。小さいうちは背の低い棚しか使えなくても、大きくなれば目線も上になって高さのある場所へ片付けられるようになります。
おもちゃの種類も変化し、形状や数もどんどん変わりますよね。そのため、小さい頃と同じ収納方法にしていると使いにくくなる場合があります。
定期的に収納方法の見直しをして、片付けやすい環境を整えてあげましょう。また、見直しのタイミングで、不要になったおもちゃの処分をしておくのもおすすめ。
子どもと一緒に必要なおもちゃをチェックし、収納スペースに入る量だけという決まりづくりをしておけば、ごちゃごちゃになってしまうのを防げるはずです。
子どもが成長してもすっきり暮らせるように片付けの習慣をつけよう
上手な声掛けや収納の仕組みづくりで子ども自ら片付けられるように!
子どもに片付けの習慣づけをさせるには、片付けが気持ちのいいことと思わせるのが大切。ママパパが上手に声掛けをして、子どもが自ら片付けたくなるように促してあげたいですね。
また、子どもが1人でも片付けやすくなる収納の仕組みづくりも大切です。どこに何をしまうのか、子どもと一緒に決めながら、ものの定位置を決めておきましょう。
子どもが片付けやすくなる収納家具を取り入れるのもおすすめ
子どもに片付けの習慣がついていれば、成長して学用品などの持ち物が増えた時にも自ら片付けられるようになるはず。成長にあわせて変化する持ち物にも対応できる収納家具があると、常に子どもが片付けやすい環境にしてあげられますね。
そんな時に役立つ収納家具をカリモクでは豊富に取り扱っています。自室を持つタイミングや入学時に揃えておくと、より進んで片付けをするようになるでしょう。
次の記事では、子どもが自主的に片付けしやすくなる、カリモクおすすめの収納家具をご紹介します。
「子どもに自分で片付けられるようになって欲しい」「大きくなってもずっと使えるものがいい」と考えているパパママは多いでしょう。
子どもの収納を見直したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。