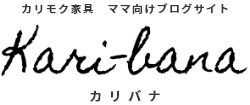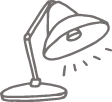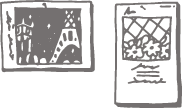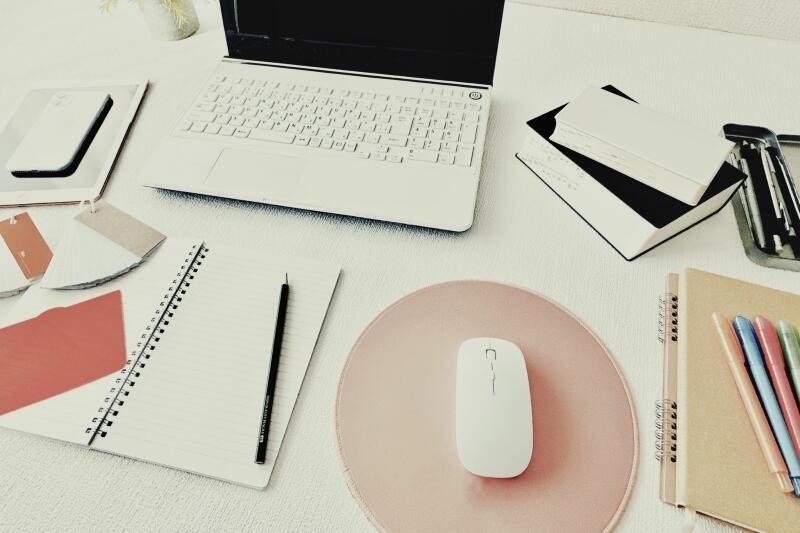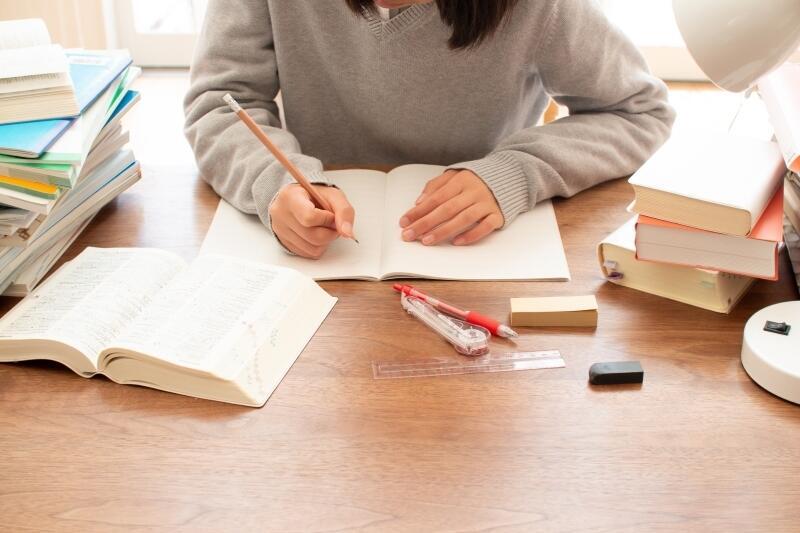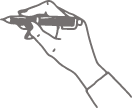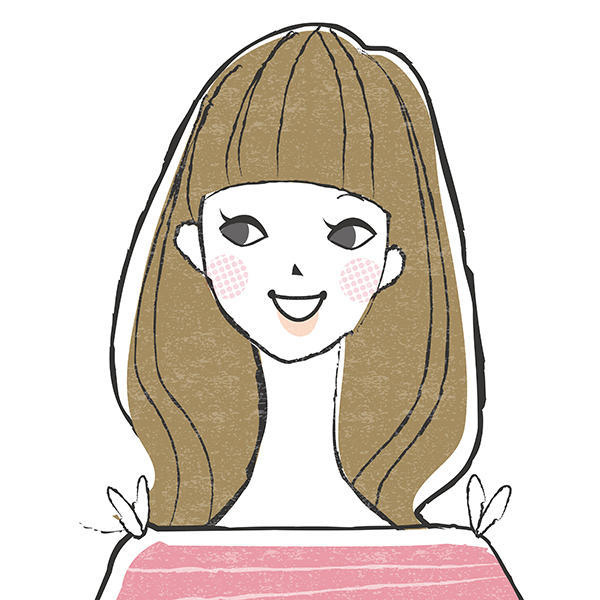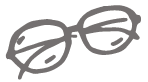魔のイヤイヤ期に突入!イヤイヤの理由と接し方を知ってイライラしない子育てを

あれもこれも「イヤ!」ばかりの2歳前後の子ども。魔のイヤイヤ期なんて言葉もよく聞きますよね。
言葉が増えてきてコミュニケーションが取りやすくなり、子どもと楽しく過ごすことができるようになってくる頃ですが、イヤイヤ期が始まってしまうとどう接したらよいか悩むママも多いはず。
そんな時は、なぜイヤイヤ言うのか、どんな接し方がいのかを知っておくと、魔のイヤイヤ期を乗り切ることができるようになるかもしれません。そんな2歳児への接し方を紹介していきましょう。
なぜイヤイヤ期はやってくる?知っておきたいアレコレ
イヤイヤ期があるのは自我が目覚めたから
ご飯を食べるのも「イヤ!」、寝るのも「イヤ!」、靴を履くのも「イヤ!」...何をするにも毎日イヤの連続で、ママも「どうしたらいいの~」と頭を抱えてしまう魔のイヤイヤ期。ついつい叱ってしまって、落ち込むこともありますよね?我が家の子どもも2歳の頃は家でも外でも寝そべって号泣し、イヤイヤ期絶好調でした。
そもそもなぜ、2歳頃になるとイヤイヤと言い始めるのでしょう?それは、自我の目覚めだと言われています。自分という存在がここにあるという自我が芽生え、自分の気持ちやしたいことの主張が強くなっていくんですね。
自分で何でもしたいという意識も強くなる一方で、うまくできなかったり、伝えられなかったりするもどかしさが子どもの中であるようです。
言葉で伝えることがまだまだ苦手だから、やりたくないことや言いたいことを全て「イヤ!」で返事してしまうのかもしれませんね。
自己肯定感を高める大事な時期でもある
イヤイヤ期は自我が目覚めた証です。そしてイヤイヤ期を経て子どもの自己肯定感は高まり、自分のことは自分で決められるようになっていきます。
これは、周囲の大人たちが「イヤ!」という子どもの主張を受け止めることで、「自分の主張が通った!」という感覚を味わうという経験をするからですね。
そう聞くと人生という規模で見ても、とても大切な時期だということをお分かりいただけるかと思います。
こうしたイヤイヤ期がやってくる理由を知った上で子どもに向き合うことで、イヤイヤ期を乗り切りやすくなるでしょう。
イヤイヤ期はいつまで続く?
2歳頃に始まるイヤイヤ期ですが、3歳を迎える頃には次第に「イヤ!」ということが減り、4歳頃にはいつの間にかイヤイヤ期が終わることが多いようです。
まるで永遠に続くように思ってしまうイヤイヤ期ですが、子育ての過程全体で見ると期間として長いわけではありません。適切な対処法を知った上で、これも貴重な経験だと思えるようになるといいですね。
そしてイヤイヤ期が終われば、自分のしたいことを正確に伝えられるようになる子どもが多いようです。自分のことを自分で決められるようになるための大事な時期なのですね。
戸惑いや怒りたくなってしまう気持ちも湧いてきてしまいますが、時には自分自身の気分転換も織り交ぜながら乗り切っていきましょう。
イヤイヤ期の接し方で大切なのは子どもの気持ちを受け入れること
イヤイヤ期の子どもの接し方でまず大切にしたいのは、子どもの気持ちを受け入れてあげることなんだそう。
子どものしたいことが可能・不可能に関わらず、「そうだね」などと、一度は肯定してあげましょう。そのあとにできない理由を説明し、一度は子どもの主張が通ったようにすると、最初から「ダメ」と否定されるより子どもも満足した気持ちになれそうですよね。
また、イヤイヤ期の子どもは伝えたいことをうまく言葉にできないので、大人が子どもの気持ちを代弁してあげることも大切にしたいですね。イヤと泣いている理由を察して、「○○したかったの?」「○○がいやだったね」と言ってあげると、子どもも気持ちを理解してもらえて安心できそうです。
保育士さんの接し方を参考にしよう

イヤという子どもの気持ちを受け止めても、すんなりとはいかないのが魔の2歳児ですよね。そこで、保育士さんが実際にやっているマネしたい接し方を紹介します。一筋縄ではいかない、魔のイヤイヤ期。イライラして叱ってしまう前に、まずは接し方のお手本を参考にしてみてくださいね。
step1.代替案や選択肢を与える
子どもの希望を叶えてあげられない時は、ダメで終わらせるのではなく、ほかの案を出したり、選択肢を与えたりしてみましょう。「今は○○できないから、帰ってきたらしようね」とか、「これは危ないからできないけど、○○か、○○ならいいよ」などしっかり話してあげると、子どもも納得してくれるかもしれません。
特に選択肢を与える方法は、何でも自分で決めたい時期に入っている2歳児に有効な手法です。自分で選んでいるという感覚を味わってもらうことで、納得につなげるのがポイントとなります。間違っても脅すような言い方はしないように注意しましょうね。
また、親として物事がスムーズに進むようにと、さまざまな選択を先回りして行ってしまいがちですが、それはイヤイヤ期真っ只中の2歳児には逆効果です。あくまで見守りやサポートをする立場でいると思ってもらえるよう、伝え方や表現には気を配り、判断自体は子どもにやってもらうように心がけておくことをおすすめします。
step2.気持ちが切り替わる対応をする
ほかの案や選択肢を与えても、子どもの気持ちが収まらないこともよくあるはずです。筆者の子どももなかなか納得してくれないことが多く、大変でした...。そんな時は、気持ちが切り替わるような対応をしてみましょう。
遊びに誘ったり、他のものに興味が向くようにしたり、お茶を飲ませてみたりと、子どもの気持ちが変わる手助けをしてみるのも効きそうな方法です。また、眠りに誘ってみるのもいいかもしれません。子どもがイヤイヤを言う時って、眠たい時に多いこともありますよね。
step3.スキンシップしたりそのまま泣かせたりして落ち着かせる
ほかの案や選択肢を与える作戦でも、気持ちを切り替える作戦でもダメっていう時はどうしましょう?寝そべって泣き叫ぶような状態になってしまうと、話も聞いてくれなくなりますよね。そんな時は、スキンシップを試してみて。
抱っこや手をつなぐなどで、子どもの気持ちが落ち着くのを待ってみましょう。それでもだめなら、しばらく放っておくのも1つの方法です。少しその場を離れ、そのまま泣かせておいてから抱っこしてあげると、落ち着くことも多いはずです。
子どもによって好きなスキンシップやタイミングには個人差があります。何度か繰り返しているうちに、イヤイヤ期の子どもへのベストな接し方が分かってくるはずです。
「イヤ!」という感情に向き合いながら、どんな時に気持ちを落ち着かせてくれるのか観察しておきましょう。
イヤイヤ期には2歳児にぴったりの遊びに誘うこともおすすめ
魔のイヤイヤ期は、自我が目覚めた子どもが成長するための通過点。
伝えたい気持ちをうまく言葉にできないから、「イヤ!」の言葉で返事してしまうんですね。親が気持ちを代弁し、子どもの気持ちを納得させられる接し方をすれば、イヤイヤ期もあっという間に感じられるかもしれませんよ。
我が家の場合ですが、時間に余裕があるタイミングでイヤイヤが始まったとき、子どもが好きな遊びに誘うことも有効手段の1つでした。大人もそうですが、イライラしたときは切り替えのために好きなことをすると、気持ちがすっと落ち着きます。
ママと一緒に遊べる子どものお気に入りの遊びが1つでもあると、とっても役立ちます。
次の記事では、2歳児にもおすすめの遊びについて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。