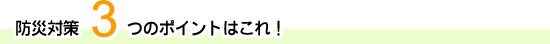 |
|
|
| 防災対策のポイントである、「身体への被害を防止すること」「逃げ道を確保して、二次被害から避難すること」について、ご紹介します。また、家具の防災機能について、詳しく解説します。 |
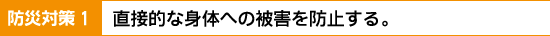 |
|
慣性力を活かす
防災対策として、家具の転倒防止をしましょう。特に「箱物家具(食器棚や収納家具等)」といわれる高さのある家具は、重心が上にあるため、少しの揺れでも転倒しやすくなります。市販の転倒防止グッズがありますが、カリモクでは、慣性力を活かすことで、転倒を防止したいと考えています。慣性力とは、家具が床と滑ることで、転倒を防ぐことです。
※阪神淡路大震災の時、その場所に弊社関西ショールームも立っておりましたが、家具自体が床を滑って動いたため、ワイングラスも倒れなかったという事例もあります。
床の素材としては、フローリングは滑りやすく転倒しにくい性質があります。一方カーペットは、下が固定されやすいため、転倒しやすくなります。床がカーペットの場合、特に転倒防止を行ってください。
|
| 背の高い箱物(食器棚やタンス)の上に、重いものや壊れやすいものを置かないようにしましょう。 |
|
|
|
〔1〕背の高い家具は、上下連結金具がついているものが多いので、必ず上下連結金具を付けてください。上下連結をしませんと、揺れの反動により、上置きが数メートルも飛ぶことがあります。上下連結のない場合は、市販の金具を裏から家具にもみつけるなどして止めてください。また、開いた扉の重みにより上置きが前に倒れることもあります。扉の開き防止に耐震ラッチも有効です。 |
|
|
〔2〕家具の上部を、転倒防止チェーンで建物と固定しましょう。箱物の上部を固定することで、箱物の下部を滑らすことができ、地震の揺力を低減させます。(転倒防止につながります。)
|
|
壁への固定は下地が大切
転倒防止チェーンなどの固定金具を取り付ける際に重要なのが壁の下地。下地のない場所ではネジが抜けてしまい、固定の意味がありません。市販の下地センサーなどで確認し、しっかりと固定することが大切です。
(下地センサーはホームセンターなどで入手できます。)
※下地に固定してある場合でも、強度など条件により抜けることもあります。 |
|
|





